事務の手引き
- 立て替え払いをしたとき
- 医療費が高額になるとき(なったとき)
- 特定疾病の療養をうけるとき
- 入院時食事負担額の減額を受けるとき
- 移送をされたとき
- 病気やけがで会社を休んだとき
- 出産のため会社を休んだとき
- 出産したとき
- 死亡したとき
- 退職後に給付を受けられるとき
立て替え払いをしたとき
| 必要 書類 |
立て替え払いのときは 療養費支給申請書(立替払等) 記入例 ■以前加入していた保険者の資格確認書等使用
■全額自己負担受診
負傷原因届 記入例 労働(通勤)災害不該当理由書 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装具等を購入したときは 療養費支給申請書(治療用装具) 記入例 ■装具
【添付書類】
■眼鏡 【添付書類】
必要に応じて添付いただく書類 負傷原因届 記入例 労働(通勤)災害不該当理由書 健康保険加入記録及び給付記録の照会について 【支給対象外となる例】
(具体例)
|
|||||||
| 支給 額 |
健康保険で認められた医療について、立て替え払いをした金額の7割~8割(年齢により変わります)が支給されます。 |
||||||
| 備考 | 【海外にいるときの保険給付〔海外療養費〕】 海外で病気やけがにより現地の医療機関で治療を受け、自費で支払った場合にも、国内にいるときと同様に健康保険組合に請求することで、払い戻しを受けることができます。ただし、治療目的で海外に行った場合の治療費については、払い戻しを受けることはできません。
|
はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき
| 必要 書類 |
【令和6年9月分まで】 療養費支給申請書(はり・きゅう用) 記入例 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用) 記入例 【令和6年10月分以降】 療養費支給申請書(はり・きゅう用) 記入例 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用) 記入例 |
|---|---|
【添付書類】
|
|
| 支給 額 |
健康保険で認められた施術(金額)について、立て替え払い(全額自己負担)をした金額の7割~8割(年齢により変わります)が支給されます。
|
| 備考 |
|
医療費が高額になるとき(なったとき)
| 必要 書類 |
【医療費の自己負担限度額を軽減したいとき】 限度額適用認定申請書 記入例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【医療費が高額になったとき】 高額療養費支給申請書 記入例 (通常は自動払いのため、申請の必要はありません。※申請書が必要な場合もあります。下記の備考欄を参照ください) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【添付書類】 【ケガの場合】 負傷原因届 記入例 【高額療養費を申請する場合】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支給額 |
高額療養費支給額(D)の計算方法 ※総医療費(A):自己負担限度額(B):あなたの支払った医療費(C):高額療養費(D)
●年間上限について 同一月の療養で①②③の順で計算する(但し、③は70歳未満の方で、自己負担額21,000円以上ある方)。
上記『高額療養費支給額の計算方法』にて計算されたア~オ欄の(B)をもとに、下記の計算方法にて支給します。
※算出額が100円未満切り捨て、1,000円未満不支給となります。 合算高額療養付加金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 限度額適用認定申請書について 医療費が入院等で高額となることがわかっている場合に、【限度額適用認定申請書】を組合まで申請いただければ、“限度額適用認定証”を発行いたします。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定疾病の療養をうけるとき
| 必要 書類 |
特定疾病療養受療証交付申請書 記入例 |
|---|---|
| 対象 となる 疾病 |
|
| 備考 | 治療を受けるときは、マイナ保険証等とともに、健康保険組合から交付された「特定疾病療養受療証」を医療機関へ提出します。 |
入院時食事負担額の減額を受けるとき
| 必要 書類 |
限度額適用認定申請書・標準負担額減額認定申請書(低所得) 記入例 |
|---|---|
【添付書類】
|
|
| 備考 | 詳細はこちら |
移送をされたとき
病気やけがで会社を休んだとき
| 必要 書類 |
傷病手当金支給申請書 ※傷病手当金は生活給の代わりとなるものです。また、医師の症状記入欄等を参考に審査いたしますので、(給料計算の起算日から締め日等)1ヵ月毎に申請してください。 記入例 |
|---|---|
【添付書類】
2回目以降の請求で、賃金の支払い等が発生していない場合、添付資料は不要ですが、賃金の支払いがある場合は、第1回目と同様に、賃金台帳(写)および出勤簿(写)が必要となります。 必要に応じて添付いただく書類 負傷原因届 記入例 健康保険加入記録及び給付記録の照会について ※1 労働(通勤)災害不該当理由書 ※1「健康保険加入記録及び給付記録の照会について」とは… |
|
| 支給 額 |
休業1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。 ☆標準報酬日額の3分の2相当額の算出方法 例:200,000円÷30日=6,666円 → 6,670円(A) ※被保険者期間が1年未満の場合、取得月から直近までの標準報酬月額の平均から日額を算出し、当組合の平均標準報酬月額と比較し、低い額での決定となります。
|
| 支給 期間 |
同一の疾病または負傷、およびそれが原因で生じた疾病に関して、連続して3日休んだとき(待期)4日目から1年6ヵ月を限度として支給されます。 ※令和4年1月1日より、支給開始日から「通算して1年6ヵ月」になります。 ※待期の完成:待期は、療養のため労務不能の日が3日間連続することが必要です。なお、3日間の中に休日または祝日があっても、その日が労務不能であれば、待期に入れることになります。 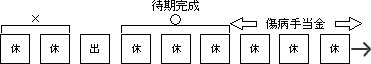 |
| 備考 | 【傷病手当金の支給条件】
【給与支払い状況の調査について】
また、傷病手当金申請期間中の給与控除(税金・保険料等)を事業主が立て替え、復職後または後日精算を行う場合、精算等が確認出来る書類(本人より事業所宛に返還されたことが確認出来る通帳のコピー等)、または台帳等を確認します。精算書類等の提出が近々に出来ない場合、事業主より支給されたものと判断し、傷病手当金の日額より控除して支給いたします。 こちらの給与支払状況の調査については、傷病手当金申請の初回および終回(満了前に復職された場合は、その復職月を対象に調査)に行います。
|
出産のため会社を休んだとき
| 必要 書類 |
出産手当金支給申請書 記入例 |
|---|---|
【添付書類】
|
|
| 支給 額 |
休業1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。 ☆標準報酬日額の3分の2相当額の算出方法 例:200,000円÷30日=6,666円 → 6,670円(A) ※被保険者期間が1年未満の場合、取得月から直近までの標準報酬月額の平均から日額を算出し、当組合の平均標準報酬月額と比較し、低い額での決定となります。 |
| 支給 期間 |
出産日(出産予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日までの期間で休んだ日について支給されます。
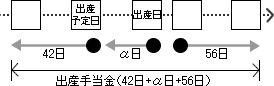 |
| 備考 | 【出産手当金の支給条件】
なお、その期間の傷病手当金が支給されてしまった場合は、出産手当金の内払いとみなされ、その額だけ出産手当金の額が減額調整されます。 |
出産したとき
直接支払制度を利用した場合(差額請求)
| 必要 書類 |
出産育児一時金支給申請書(差額請求) 記入例 |
|---|---|
| 【添付書類】 ※『出産育児一時金直接支払通知書』が健保からお手元に届いている場合は不要
|
|
| 支給 額 |
出産育児一時金の支給額(1児につき50万円または48.8万円)に満たないときの差額が支給されます。 |
受取代理制度を利用する場合
| 必要 書類 |
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) 記入例 |
|---|---|
【添付書類】
|
|
| 支給 額 |
受取代理人となる医療機関等へ1児につき50万円または48.8万円の支給、被保険者へ出産育児一時金の支給額(1児につき50万円または48.8万円)に満たない場合は差額が支給されます。 |
直接支払制度または受取代理制度を利用しなかった場合
| 必要 書類 |
出産育児一時金支給申請書 記入例 |
|---|---|
【添付書類】
|
|
| 支給 額 |
1児につき50万円または※48.8万円(※妊娠22週(154日)以前の出産、産科医療補償制度未加入の医療機関または海外での出産の場合) |
| 備考 | 【海外出産の場合の添付書類】 |
死亡したとき
埋葬料 家族埋葬料
| 必要 書類 |
埋葬料(費)支給申請書 記入例 |
|---|---|
| こちらをご覧ください。 | |
| 関係 する 届出 |
【被保険者が死亡したとき】 被保険者資格喪失届 記入例 【被扶養者が死亡したとき】 被扶養者(異動)届 記入例 |
| 支給 額 |
被保険者・被扶養者ともに一律50,000円が支給されます。 |
| 備考 | 埋葬料(費)については、死亡の原因を問わず支給されます。 ただし、業務上・通勤途上による死亡が原因の場合は支給されません。 |
埋葬費
| 必要 書類 |
埋葬料(費)支給申請書 記入例 |
|---|---|
| こちらをご覧ください。 | |
| 関係 する 届出 |
被保険者資格喪失届 記入例 |
| 支給 額 |
埋葬料の範囲内(上限50,000円)で、実際に埋葬にかかった費用が支給されます。埋葬にかかった費用とは、具体的には霊柩代、霊柩車代、火葬料、僧侶の謝礼、葬壇一式料などで、葬式の参列者の接待費、香典返しなどは含まれません。 |
| 備考 | 埋葬料(費)については、死亡の原因を問わず支給されます。 ただし、業務上・通勤途上による死亡が原因の場合は支給されません。 |
退職後に給付を受けられるとき
傷病手当金
| 必要 書類 |
傷病手当金支給申請書 記入例 ※喪失日以降の事業主の証明はいりません。 |
|---|---|
【添付書類】
|
|
| 支給 額 |
休業1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。 ※在職中に受給されていた日額となります。 |
| 備考 | 継続して1年以上社会保険の被保険者であった人が資格を喪失し、次のいずれかに該当する場合は、当組合が労務不能と認めた方に限り、傷病手当金の支給期間が満了するまで受けられます。※任意継続の期間は除きます。 【傷病手当金の支給条件】
|
出産手当金
| 必要 書類 |
出産手当金支給申請書 記入例 ※喪失日以降の事業主の証明はいりません。 |
|---|---|
| 支給 額 |
休業1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。 ※在職中に受給されていた日額となります。 |
| 備考 | 継続して1年以上社会保険の被保険者であった人が資格を喪失し、次のいずれかに該当する場合は、労務不能が続く間、出産手当金の支給期間が満了するまで受けられます。 【出産手当金の支給条件】
|
出産育児一時金
| 必要 書類 |
※下記のいずれか 出産育児一時金支給申請書(差額請求)(直接支払制度を利用した) 記入例 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) 記入例 出産育児一時金支給申請書(直接支払制度を利用していない) 記入例 |
|---|---|
| 【添付書類】は「手続き」をご覧ください。 | |
| 支給 額 |
1児につき50万円または48.8万円 (直接支払制度を利用して、出産費が上記金額に満たなかった場合は、その差額分の請求可能) |
| 備考 | 継続して1年以上社会保険の被保険者であった女性被保険者が資格を喪失した後、6カ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。
|
埋葬料(費)
| 必要 書類 |
埋葬料(費)支給申請書 記入例(埋葬料) 記入例(埋葬費) |
|---|---|
| 支給 額 |
上限50,000円が支給されます。 |
| 備考 | 被保険者であった人が、次のいずれかに該当するときは、埋葬料(費)が受けられます。 |




